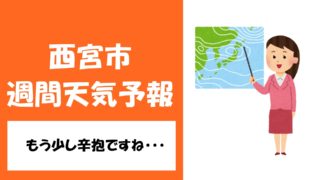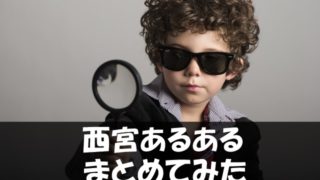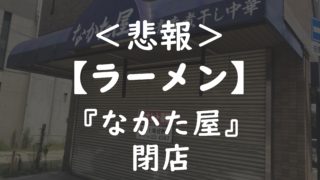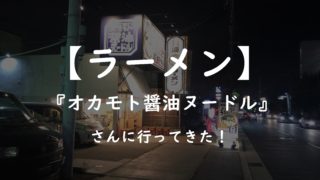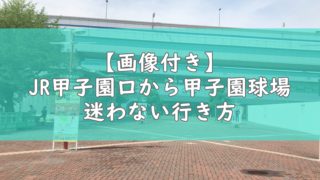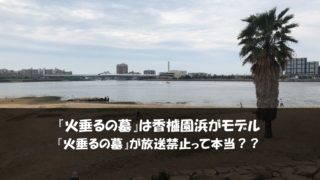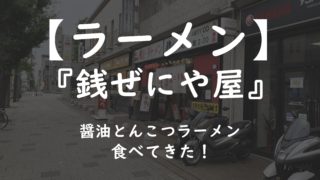東京・恵比寿10億円不動産を他人が相続
また土地と相続に関するしどろもどろしたニュースが報道されていますね。
「伯母の遺言書が書き換えられ、時価10億円相当の不動産が他人の手に渡ることになりました。本当に許せません」。取材に応じた鈴川恵子さん(仮名)=(55)=は怒りに震える。伯母は東京・恵比寿に土地や建物、賃貸マンションの部屋を複数所有したまま今年4月に94歳で死去。公正証書遺言には、不動産は全て知人男性に譲ると記されていた。
ただ問題は、遺言書を作成したときに伯母は認知症を患っていたという点である。このような判断能力が欠如している場合での遺言書の効力は、いったいどのように判断されるのか気になったのでまとめてみた。
今回の話のおおまかの流れ
①「私が●んだら、全財産を譲ると約束してくれた」(鈴川さん)
→平成26年作成の遺言公正証書に記述(叔母は2024年4月に他界)
➁地元不動産会社の男に平成31年作成の遺言公正証書に基づき寄贈
③不動産の処分禁止の仮処分を東京地裁に申請
→2024年11月に認められる

遺言公正証書とは、●後の財産分与などを書き記す遺言を公証人が公的権限に基づいて作成することだよ。相続をめぐる法的争いを未然に防ぐために作成されるよ。
今回の件は親族の方は本当に気の毒な話である。
認知症の状態で書かれた遺言書は有効なのか?

「新たな遺言公正証書が作成された31年当時、伯母は認知症で『要介護5』の認定を受けていたのです。まともな判断能力のもとで、伯母が遺言書を残したとは思えません」(鈴川さん)

要介護5はもっとも思いレベルで、食事や排せつなど日常生活のほぼすべてに支援が必要とされるレベルです。
ただ、だからと言って認知症であるから遺言書は有効ではない、すなわち無効であるというわけではありません。むしろ、無効と判断されるケースは稀なようです。
認知症であったかどうかということが問題なのではなく、遺言能力があったかどうかといことが法的には重要です。
もちろん①はクリア。問題は➁となりますが、今回のケースでは「公正証書遺言」で作成しております。証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を話すことで作成するため、公正証書遺言が形式不備によって遺言が無効になる可能性は、基本的にありません。
が、、、、「公正証書遺言」は
公証人の関与
- 公正証書遺言は、公証人が立ち会い、その内容が合法であることを確認し、作成する遺言です。
証明書の内容の確認
- 遺言者は自分の意思を公証人に伝え、その内容を基に遺言が作成されます。公証人は、遺言が法律に基づいて正しく作成されているかを確認
3.証人の立ち会い
- 公正証書遺言には、証人として2人以上が会う必要があります。この証人は遺言者の親族です
この3の部分に問題があったと判断されているのではないかと推測します。
事前準備が必要
このような相続問題が起きないようにするためにはやはり生前の間(あるいは意思がはっきりとしている)時にきっちりと話をすませておくことがベターです。今回の場合は親族の方からしてみれば晴天の霹靂であったとは思いますが、土地という大きな遺産を譲る譲らないという話はやはり最新の注意を払っておくべきだったとも思います。相続問題でゆくゆくいざこざが起こらないよう事前に準備しておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。